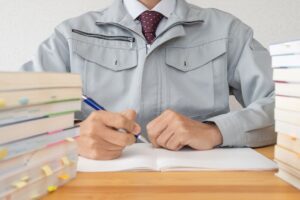
建設業許可が必要なケースをまず把握する
建設業の許可は、一定規模以上の工事を請け負う会社や個人事業に必要です。元請・下請を問わず、500万円(消費税含む)以上の工事や、建築一式工事で1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を受注する場合は許可が求められます。小規模な修繕のみであれば不要なこともありますが、将来的な受注拡大や元請からの信頼獲得を考えると、早めの取得が有利です。
一般許可と特定許可の違い
一般許可は下請への発注が3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)を前提とする一般的な事業者向けです。特定許可は大規模な下請発注を行う元請向けで、財務基準も厳格です。まずは一般許可を取り、事業規模が拡大してから特定へ移行するのが定石です。
業種区分の考え方
許可は「土木一式」「とび・土工」「塗装」「電気」など29業種に分かれます。主力工事の種類と将来の受注計画から、必要な業種を選ぶのがポイントです。無理に多く申請するより、コア業種を確実に押さえる方が審査・維持の負担を抑えられます。
許可要件の4本柱を整理する
ここからは、審査で重視される基本要件を順番に見ていきます。用語は難しく見えますが、要点さえ押さえれば準備は進めやすく、専門家に依頼する場合も判断が早くなります。
経営業務の管理責任者(経管)
申請業種に関し、一定年数の経営経験がある人物を置く必要があります。法人なら役員、個人なら事業主または支配人が該当します。経験の証明は、登記、許可台帳、請負契約書などの資料で行います。
専任技術者
各営業所ごとに、該当業種の実務経験年数や国家資格(1級・2級施工管理技士など)を満たす技術者を常勤で配置します。資格で満たす方法が最も分かりやすく、採用・育成計画と連動させると中長期の競争力につながります。
財産的基礎
一般許可では自己資本の充実や資金調達力が求められます。具体的には、直近の決算書や残高証明で支払い能力を示します。赤字決算でも、増資や資金調達で要件を満たせる場合があるため、早めの対策が有効です。
欠格要件の不存在
暴力団排除、建設業法違反歴、役員の欠格事由などがないことが前提です。コンプライアンス体制の整備は、許可更新や元請評価にも直結します。
申請から取得までの流れと期間
要件を満たしているかを確認したら、必要書類を揃えて都道府県知事許可または大臣許可を申請します。書類の不備があると審査が延びるため、チェックリスト化が効果的です。
準備書類の代表例
登記事項証明書、納税証明、決算書、経管・技術者の経歴証明、工事契約書・請求書、常勤性を示す社会保険資料などが中心です。営業所の実在性を示す賃貸借契約や写真も求められます。
審査期間の目安
自治体により差はありますが、受理から1~2か月程度が一般的です。繁忙期や書類の補正が入るとさらに日数を要します。新規の繁忙期を避け、決算後の数字が確定してから動くとスムーズです。
よくあるつまずきと回避策
次に、現場で起こりやすい失敗例を押さえましょう。事前に手当てしておけば、申請のやり直しや受注機会の逸失を防げます。
技術者の要件不足
担当者の実務年数が要件に届かない、資格区分が業種に合っていないといった齟齬が起きがちです。採用時に資格台帳を整備し、現スタッフの受験計画を立てておくとリスクを減らせます。
営業所要件の見落とし
「机と電話があるだけ」では不十分なケースがあります。事務所の独立性、標識掲示、帳票類の整備など、審査視点でチェックすると安心です。
財務要件のタイミング
決算直後に自己資本が不足する場合、増資や借入の実行時期で評価が変わります。金融機関との調整を含め、申請月から逆算して資金計画を引くのがコツです。
許可が採用(求人)にもたらすメリット
最後に、許可取得が人材獲得にどう効くかを確認します。求職者は「安定」「成長性」「資格活用」を重視するため、許可の有無は応募率や内定承諾率に影響します。
求人原稿での打ち出し方
一般許可を明記し、担当業種、配置する専任技術者の体制、資格手当や受験支援制度を具体的に示します。将来的に特定許可を目指すロードマップを添えると、キャリア志向の人材に響きます。
教育・評価制度との連動
施工管理技士や電気工事士などの資格取得を評価・報酬に反映させ、現場OJTと講座費用補助をセットにします。許可維持に必要な体制を、社員の成長機会として可視化すると、定着率の向上にもつながります。
安全・法令順守の訴求
許可事業者として安全教育、社内監査、協力会社管理を徹底している点を示すと、未経験者にも安心感を与えます。現場見学や体験入社の導線を用意すると応募ハードルが下がります。
